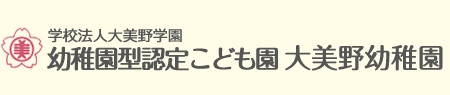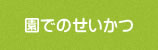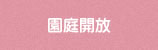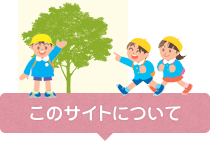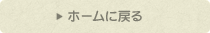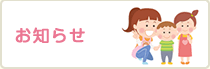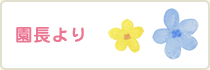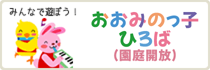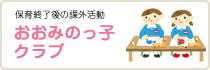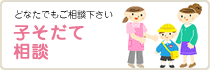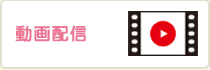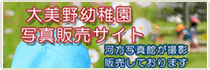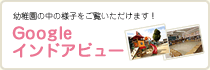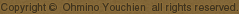9/16(金)台風のまま、上陸?!
またしても、「なんということでしょう」という事態が発生です。
温帯低気圧に変わって日本海へと、数日前の天気予報で聞いていたのですが、
ホントに「なんということでしょう」です。
園庭には朝から、水たまりができています。
園では、運動会の打ち合わせ・準備を滞りなく行う予定でしたが、その前に、風雨対策をせねばならない状況となりました。幸い、高台にあるので浸水は大丈夫ですが、永年経過で老朽化した園舎、心配はつきません。無事、通り過ぎてくれること、祈りたいと思っています。
自宅は、朝からある限りの雨戸を閉め、植木鉢を避難させてきました。
できる準備は整えて、自然の猛威に対峙しましょう。
「備えよ常に!」大事なことです。