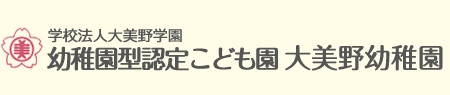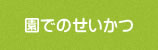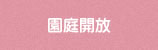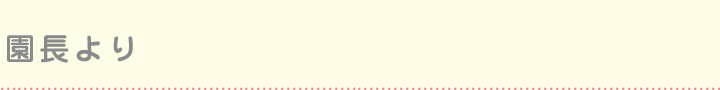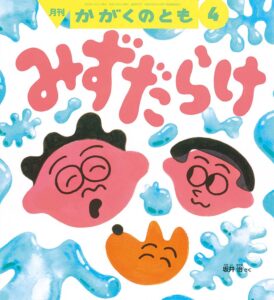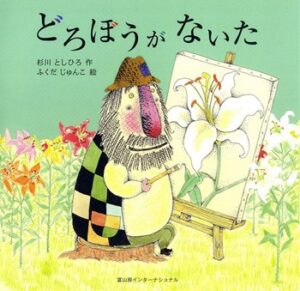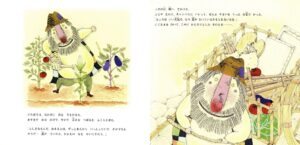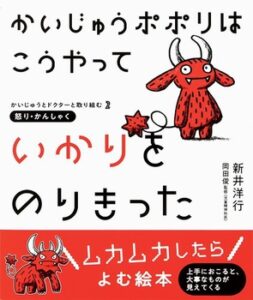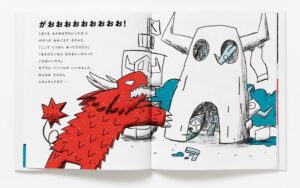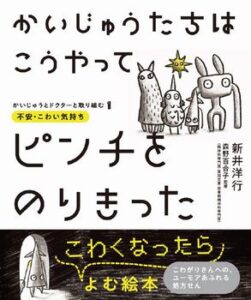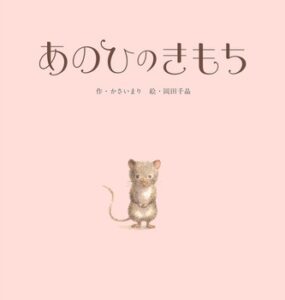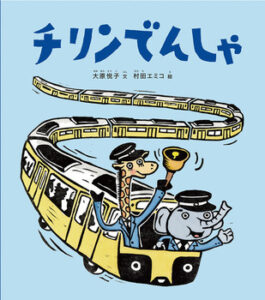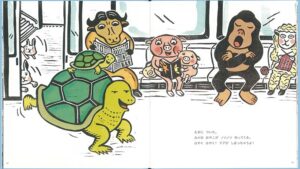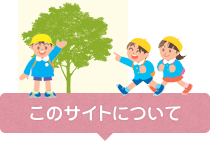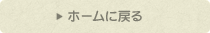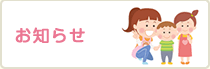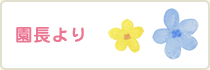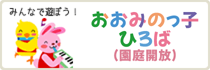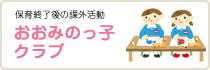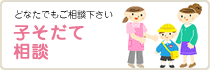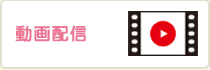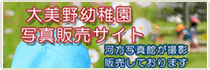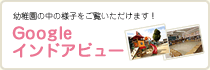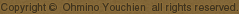2/9(月)だれの落とし物?
園庭にハンカチが一枚。落とし物が先生に届きました。名前のないハンカチなので他の先生たちに尋ねてみましたが、だれのものでもなかったとのこと。
子どもたちに尋ねると・・・「園長先生ちゃう?園長先生が好きそうな模様やで」とのこと。
いやいや・・・と思いながら、最後は職員室に届けられました。
なんと、大正解です。私のハンカチが、ちゃんと手元に戻ってきました。
子どもたちが見る目、侮れませんね。素晴らしい観察力を持つ子どもたちに拍手です。
今日の幼稚園は朝からお休みの連絡で大わらわ!劇遊びに向けてみんなで心ひとつに練習に励んでいたので、残念ですが致し方ありません。
元気になって早く戻ってくれる日を待ちたいと思っています。いつも満員の園庭も砂場も、寂しそうです。